HILLS CAST
“東京をおもしろくするアイデア”を持ったゲストをお迎えしてお届けする「HILLS CAST」は、J-WAVEのラジオ番組「森ビル presents 東京コンシェルジュ」内で放送していた森ビルのラジオCMです。
※掲載内容は、取材・放送時点のものです。
都市から学び、生まれる建築(第3回)
2009年02月13日
今月のゲスト:建築家 隈 研吾さん
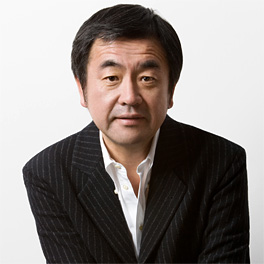
建築家の隈研吾さんが現在抱えているプロジェクトは、海外だけで40件以上に及ぶ。世界中の都市を渡り歩く日々のなか、隈さんは新しい土地との出会いを特 に大切にしているという。白紙の状態でその地を踏み、現地の人々と食事を共にして、コミュニケーションを取ることを欠かさない。第三者の立場では知り得な い文化の奥深くに入り込み、はじめて触れられる都市の本質。
土地そのものから学ぶことの重要性を、隈さんが語った。
第3回 アメリカ中心の建築観に反旗を翻す
六本木ヒルズの上で「アーキラボ」という展覧会をやったことがあります。簡単に言うとアーキラボというのはね、フランスがアメリカ中心の建築観とか都市観に反旗を翻して、もう1回、ヨーロッパ中心の建築の世界観みたいなものを世界に問うて、アメリカをひっくり返してやろうという企てなんですよ。
そういう企てで、建築の模型とか図面をコレクションしているアーキラボという組織がフランスにあって、彼らはそのぐらいの志でやっているから、1個1個の建築のセレクションにしろ、模型のセレクションにしろ、毒が効いている。「アメリカ型の都市だけが都市じゃないぞ」というような、こう、毒というか、批評精神みたいなのが効いているからね。コレクションが、見ていて楽しいのですよね。
今はそのアーキラボの中心的な人物がポンピドゥセンターに移って、ポンピドゥセンターの建築の中心人物になっていて、また今度、日本の建築展を数年後にポンピドゥセンターでやるのです。やはり、そういう「アメリカが支配した20世紀の都市をひっくり返してやろう」という目で、「日本とも仲良くしようぜ」みたいなことを言ってきているからね。彼らの動きにはちょっと目が離せないという気がしますね。
建築にも、毒が必要だ

僕も自分で1980年代ニューヨークに住んで、「やっぱりニューヨーク、確かに刺激的だけれど、20世紀、アメリカ型の都市じゃないものを俺たちはつくらなきゃいけない」って、ものすごく強く思った。住んでみて、余計に強く思ったのですね。
それで、例えば日本的な都市とは何かとか、日本的な自然との共生は何かとか、そういうことを考えるようになったのも、アメリカに住んで、アメリカに対する何か批評的な目がそこで生まれてから、日本を再発見したみたいな、自分のプロセスがあるんですね。
何か建築というのは、そういう批評精神というか、ある意味での毒みたいなものがないと、ピリッとしたものにならないのではないかなと思いますね。
プロフール
建築家/1979年、東京大学建築学科大学院修了。1990年隈研吾建築都市設計事務所主宰。
主な作品に「水/ガラス」(アメリカ建築家協会ベネディクタス賞受賞)、「森舞台/宮城県登米町伝統芸能伝承館」(日本建築学会賞受賞)、「那珂川馬頭町広重美術館」(村野藤吾賞、林野庁長官賞受賞)、「石の美術館」(インターナショナル・ストーン・アキテクチャー・アワード受賞)。現在も世界中で40以上のプロジェクトを進行中。
