HILLS CAST
“東京をおもしろくするアイデア”を持ったゲストをお迎えしてお届けする「HILLS CAST」は、J-WAVEのラジオ番組「森ビル presents 東京コンシェルジュ」内で放送していた森ビルのラジオCMです。
※掲載内容は、取材・放送時点のものです。
都市から学び、生まれる建築(第1回)
2009年02月01日
今月のゲスト:建築家 隈 研吾さん
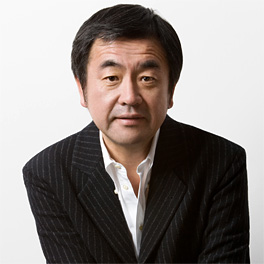
建築家の隈研吾さんが現在抱えているプロジェクトは、海外だけで40件以上に及ぶ。世界中の都市を渡り歩く日々のなか、隈さんは新しい土地との出会いを特に大切にしているという。白紙の状態でその地を踏み、現地の人々と食事を共にして、コミュニケーションを取ることを欠かさない。第三者の立場では知り得ない文化の奥深くに入り込み、はじめて触れられる都市の本質。
土地そのものから学ぶことの重要性を、隈さんが語った。
第1回 都市とはパーティである
都市というのはパーティだと思うのです。
例えば「銀座」って、そういうパーティにみんな呼ばれて集まってきているわけね、ティファニーが集まったりとか、ルイ・ヴィトンが集まったりとか。そのパーティの出席者というのは、パーティの中で自分がどう振る舞えばいいかということを、うまく考えなければいけないのですね。
何を着ていったらいいか、そこで何をしゃべったらいいか。そういう全体の振る舞いがちゃんと洗練されていて、そういうメンバーが集まってくると、その場所自身が華やかな気持ちのいい雰囲気が出てくるわけで。
そういうパーティとしての、一種の社会的なコミュニケーションの場所としての都市というのが、どうも日本人はまだ苦手のような気がするな。例えば銀座にしろ、六本木にしろ、表参道にしろ、随分そういうパーティ的なしつらえは始まっているけれど、いざその場所に行ったときに、本当にみんながそれにふさわしい振る舞いとして全体を盛り上げているかというと、ちょっと疑問のところもある。1人だけ妙に目立とうとしていたり、脇ではうんと沈んでしまっていて参加しない人がいるとか、何かそういうバラバラ感が、まだまだ日本の都市にはありますね。
六本木ヒルズに想うこと

六本木ヒルズはね、ビジョンの大きさみたいなのがあるからね。いろいろな日本の大きな開発を、僕らのデザイナーの目で見てみると、六本木ヒルズぐらい志が高くて、「あしたの都市はどうあるべきか」ということを見据えている開発って、そんなたくさんはないんですよね。
21世紀の都心型というのは、いろいろな多要素が混在していて、住まい、レジデンシャルな細やかさもあるけれど、商業的な華やかさもある。そういう開発をつくろうという志の高さが、あれだけストレートに実現している例は、世界にもそんなにないですよね。そういう意味で、僕は六本木ヒルズのことをすごく評価しているのですね。
僕、森さんはアーティストだと前から思っていたんだけれど、やっぱりこれからの時代には、ディベロッパーって、アーティスティックなセンスというのが絶対要るんですね。要するにビジネスのセンスとかファイナンシャルのセンスというものだけでは、逆にビジネスとしてうまくいかないので、アーティスティックなひらめきとか、そのひらめきをどうしても実現するという強い意思みたいなのがないと、これからの都市開発というのはうまくいかない。そういう時代なんですよね。今アートというものとビジネスというものが、すごく距離が近くなっているような気がするな。
プロフール
建築家/1979年、東京大学建築学科大学院修了。1990年隈研吾建築都市設計事務所主宰。
主な作品に「水/ガラス」(アメリカ建築家協会ベネディクタス賞受賞)、「森舞台/宮城県登米町伝統芸能伝承館」(日本建築学会賞受賞)、「那珂川馬頭町広重美術館」(村野藤吾賞、林野庁長官賞受賞)、「石の美術館」(インターナショナル・ストーン・アキテクチャー・アワード受賞)。現在も世界中で40以上のプロジェクトを進行中。
